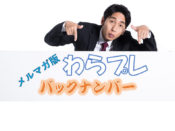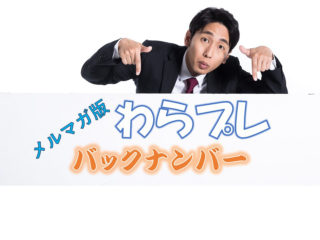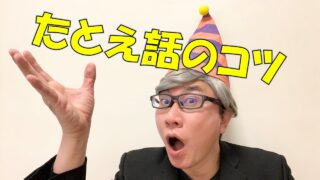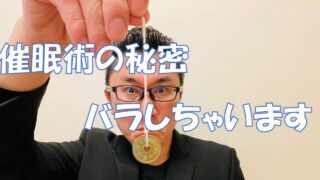読書感想文は感想を書いちゃダメ!?(わらプレvol.178)

おはようございます、桑山です。
昨日は「幕末地球防衛軍」というお芝居を観て来ました。
ライトノベルを書いてみたいと思っている僕には、とても勉強になりました。
詳しいことは、また別の機会に。
さて、昨日は「読書感想文は本を売るための忖度文章で(極論!!)」という話をしました。
今日はこれについて説明したいと思います。
昨日の要点を整理しましょう。
・その本を読みたくなる読書感想文にする
・あらすじ紹介は所詮二次情報。これ自体に魅力は少ない
・そのために、自分の体験や考え(一次情報)を重ねる
さて、最大の疑問点は「なぜ読みたくなるような感想文」にしなければならないのか? というところだと思います。
それには2つの理由があります。
1.そっちの方が簡単だから。
2.そっちの方が将来、役に立つから。
まず1の「簡単」から説明しましょう。
ここで質問です。
あなたが長年愛用しているものって何ですか?
ボールペン・万年筆・自動車・時計・アクセサリー・メガネ・洋服・バッグ・ラーメン屋・イタリヤ料理店……
なんでもいいんです。
つい、毎回このシャンプーを買ってしまう。
買う時は必ずこのメーカーのものと決めている。
そんなものは、ありますか?
では、更にお聞きします。
「それを使っての感想はどうでしょうか?」
え?
感想?
ま、まぁ好きですよ。
う~~ん、なんというか……使いやすいしね。
なんて、歯切れが悪くなるのではないでしょうか?
では、質問を変えましょう。
「その愛用しているものの、自分が気に入ってる理由を、一番の親友に説明してみて下さい。出来れば、その親友が使ってみたくなるように」
どうでしょう?
さっきよりは言葉が出やすくなるのではないでしょうか?
感想と言われると漠然としていますが、「気に入っている理由」と言われれば途端に明確になってきます。
人間は「何を」「誰に」伝えるかがはっきりすると、上手い下手はあっても、伝えることに迷うことが少なくなります。
さらに日本人は「自分のこと」をアピールするより、自分以外のものの良い事をアピールする方が得意です。
「自分の長所をアピールして下さい」より「親友の長所をアピールして下さい」の方が抵抗ないですよね?
そんな訳で、「この本の感想を述べる」より「この本の面白さをアピールする」方が簡単なのです。
2番目の理由。「そっちの方が将来、役に立つから」について。
社会人になった時のことを考えてみて下さい。
文部科学省の提唱するように「読んだ文章を理解して自分の考えや感想を持つ」機会って、どんな時でしょうか?
そもそも、そんな機会って本当にあるんでしょうか?
そりゃ、あるに決まってるじゃん!!
例えば……
・上司に企画についての意見を求められたとき とか
・お客さんに商品を薦めるとき とか
・取引先を説得して契約をクロージングまでもっていくとき とか……
でも、もう一度立ち止まって、よく考えてみて下さい。
それって「自分の考えを持って伝え」れば、上手くいくのでしょうか?
それより
・その企画の良さを見つけ出してアピールする
・その企画に「こういう改善を加えたらもっと良くなる」ということをアピールする
・お客さんに商品の良さをアピールする
・この契約を結ぶことのメリット(良さ)を伝える
ということなのではないでしょうか?
それだけではなくて、例えば誰かの協力を仰ぐ時にも、好きな人と仲良くなる時でも、この「良さを見つけてアピールする」というスキルが必要だと思いませんか?
つまり、社会人になって(というか生きていく上で)一番必要な能力は「良さを見つけて褒める」というスキルだと思うのです。
このスキルは、訓練すれば出来るようになりますが、訓練しなければかなり難しいスキルだと思います。
実際、僕も今、ちょっとずつ鍛えてるところですが、なかなか習得が難しい。
ちょっと気を抜くとすぐに「悪いところ」や「欠点」ばかりに目がいき、ダメ出しをしがちです。
ダメ出ししてくる人と褒める人、どっちが皆から好かれて生きやすいと思いますか?
だからこそ、幼い頃からこのスキルを習得するためにも読書感想文を活用するのがいいと思うのです。
【今日の結論】
読書感想文は感想を書くのではない。
自分の考えや体験を混ぜながら、その本を読みたくなるような文を書く。
そこまではわかったけど、なんか難しそう。
そう思っちゃいました?
ステップを踏めば簡単です。
1.「好きなゲームとか遊びとかアニメとかスポーツとか、ある? 食べ物でもいいけど」
2.「それの良さって詳しく教えて」
3.「じゃ、僕がそれをやってみたくなるように誘ってみてよ」
4.「次は僕がこの本を読みたくなるように誘ってみて」
こんな感じ。
さあ、今日はどんな物、どんな人の「良いところ」を見つけてみようと思いますか?